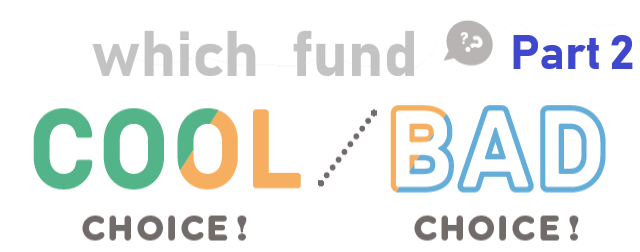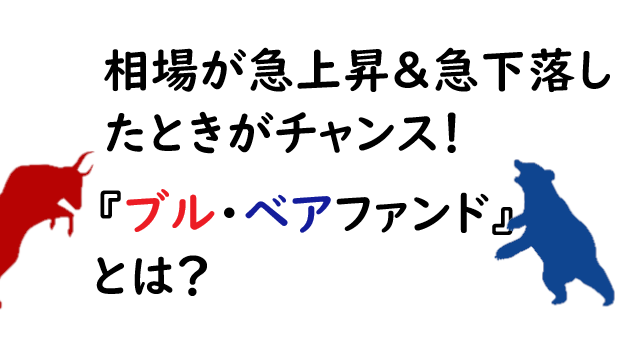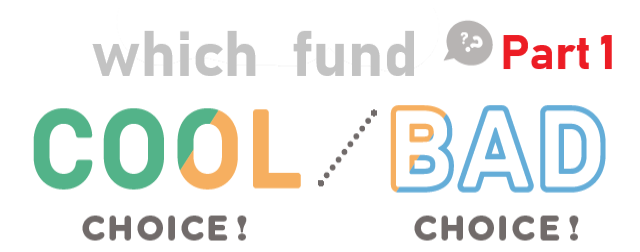投資信託を選ぶポイント
7)評価情報の活用

ファンド選択時の有力な情報として、「投信の評価情報」があります。
複数の投信評価会社が、星印や特定の記号を用いてファンドの過去の実績についての評価を投資家に提供しています。ただし、評価情報はあくまでも過去の実績についてのもので、将来の成績を予測しているわけではありませんから、使い方には注意が必要になります。
一般的に投信の評価は
①分類の基準設定と各ファンドの分類
②リターンとリスクの計測
③リターンとリスクの両面から見た総合ポイントの算出
④ランキング
⑤上位から順番に星印や記号をつける
の手順に沿って行なわれます。最初に行なうのはファンドの分類ですが、これは例えば日本株ファンドと米国株ファンドを同じ土俵で比べても、投資対象自体のリターンの違いが大きいため、ファンド同士の比較がしにくいからです。
最終的な評価は、リスクとリターンの両面から見た総合評価となりますので、評価会社は「安定的に良好なリターンをあげてきたファンド」をよいファンドとしていることが多いといえます。
その結果、例えば「短期的に素材関連株の値上がりが予測できるので、その上昇を捉えられるファンドを購入したい」というような場合には、評価情報はあまり役立たない可能性が高いといえるでしょう。
つまり、投信の評価情報を使う場合には、まず「どのようなファンドを買いたいのか」「どのようなスタンスで投資するのか」が重要となります。漠然と「何でもいいから星印の多いファンドを」といった選び方をすると、自分のニーズと合致しないファンドを選んでしまいかねません。代表的なデータとその読み取り方については、投資信託の選び方(応用編)でししたいと思います。
(8)長期的なポートフォリオ運用を心がける!

投資信託は、それ自体が分散投資効果を得られる運用商品です。しかし、それぞれのファンドの値動きは、すでに説明してきましたように、投資対象や運用方法によって、かなりぶれが大きいものも存在します。だからこそ「投資信託を買えば、それだけでリスク分散ができて安心」などと考えてはいけません!!
例えば、日本株ファンドに投資する場合には、個別銘柄ひとつを選んで投資するよりも、通常はリスクが低減されますが、日本の株式市場全体が下落した局面では、その影響を免れることは極めて難しいでしょう。
もちろん、ひとつのファンドの中で日本を含む全世界の株式や債券などを対象にして、バランスをとりながら、投資を行なうタイプのファンドもあり、この場合はよほどの異常事態が発生しなければひとつのファンドだけで万全といえるかもしれません。しかし、実際には一社で投資対象となるマーケットすべてについて優れたアクティブ運用を行なえるという運用会社は、なかなか見当たらないものです。
いずれにしても、自分の金融資産のコア部分についての長期的な運用を考える場合には、値動きの異なる複数のファンドを組み合わせることによって、「分散投資」を行なうことが原則になります。
以上3回に分けて投資信託の選ぶべきポイントについて解説していきました。
いかがだったでしょうか??
「うーーん。分かったような分からなかったような・・・」というあなた
「そこまでいうなら、お盆休み返上で(笑)とことん解説いたします!!」
次回の記事からは実際の目論見書を参考にしていきながらその見方についてさらに分かりやすく説明いたしますので要チェックです。