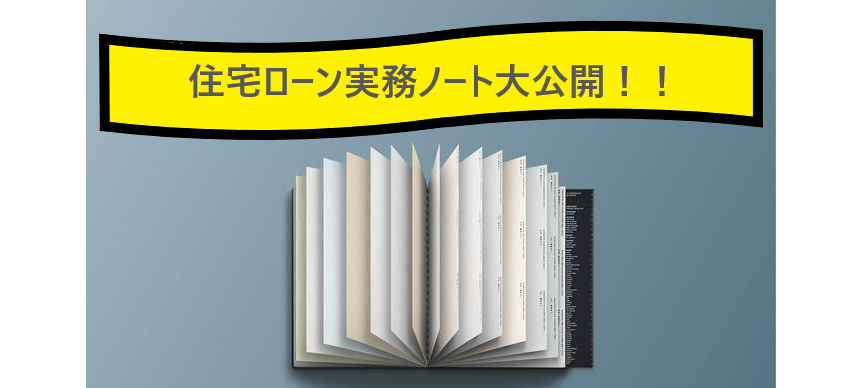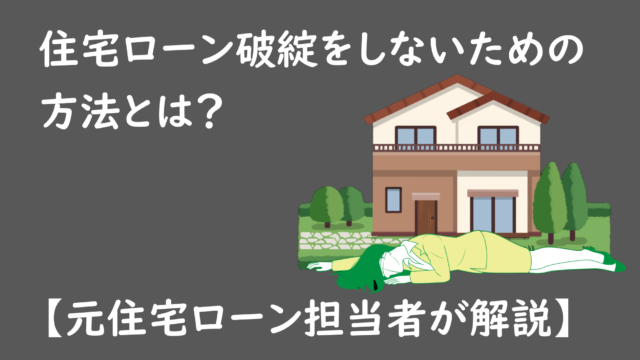入行から約半年たち、10月には正規採用される銀行マンも多数いるであろう。
そんな、新人銀行マンにとっての最初の関門が住宅ローンである。
いままではカードローンや店頭で普通預金の開設とかはたまたまだ後方でオペレーションしている人も多いかもしれないが、住宅ローンは不動産業者や司法書士、売り主、買主などなどたくさんの人とコミュニケーションをとりながら業務を進めていかなければならない。
特に担保関連は事前にその知識がなければまったくわからず、住宅ローンの借換推進をお客さんに勧めておきながら瑕疵担保のため貸せませんでしたなんてことが起こってしまう。
ネットにはなんとなく住宅ローンの流れは載っているがどういうときにどんな書類を取入れたらいいかわからないという人も多いだろう。実は自分もその一人で先輩や上司、お客さんに怒られながら改善していき作った事務手続きノートは銀行員とはいえないほど大雑把な性格の自分には必要不可欠なものであった。
今回久々にEvernoteを開けるとそのノートがでてきたので、一人でも不幸な銀行員が出ないように自分が当時住宅ローン担当であったときまとめたノートを悩めるみなさんに大公開しますね!!!

Contents
住宅ローン仮申込編
<ヒアリング事項>
・現在の段階(見積もり書はすでにもらっているのか・申込金は支払ったのか・売買契約はしたのか(手付金は物件価格の5%が多い)・着工、完成予定はいつか)
・建築地(市街化区域かどうか)
・土地(既に購入済みか、同時購入するか)
・建築会社名
・建築費用
・希望融資金額
・希望融資期間(定年までに完済を推奨)
・頭金(自己資金)
・年収
・勤務先
・現在の貯蓄合計額(いざというとき200万は残しておくことを推奨)
・家族構成
・夫のみで返済するのか、夫婦で返済していくのか(ダブルスプランまたは妻が連帯債務者になるのか)
・現在の住まい(実家、マンションなのか(家賃は月額いくらか)
・親からの援助資金などはあるか(贈与の優遇税制参照あり)
・毎月いくらまでなら無理なく返済できるか
・諸経費もローンに含めるか【新築(物件価格の5~7%)、】
・家、土地の持ち分について
<諸費用>
・契約書にはる印紙代(1000万円以上5000万円以下の場合、印紙代は2万円)
・不動産登記にかかる費用(登録免許税:1/1000、登記費用、司法書士報酬等)
・不動産所得税
・保証料
・火災保険料、地震保険料
・抵当権設定費用
<基本事項>
・融資金額:100万~5000万(10万単位)
・融資対象者:満20歳以上65未満かつ対象年齡が満75歳6ヶ月以内
・団体信用生命保険に加入できる方。
<注意事項>
・団信:50歳以上は地銀協団信しかはいれない。50歳以下は○○を案内。
・家族構成で子供が3人以上または65歳以上の高齢者と同居の場合は子育て高齢者の金利優遇プランを案内する。
・現在賃貸の方は二重ローンにならないよう据え置き期間を設けることを考慮する。
<調達計画>
・諸費用についていくらかかるか概算する。
・借入人がいた場合贈与税に関すること、持ち分についてはどうか話す。
・期間、担保順位(壱位しか認めない)を書いてもらう。
<申込内容>
・借入期間が完済時75歳超えないか。
・元利均等、変動金利、保証料形態についてパンフレット利用して話す。
・つなぎ融資(着工金、中間金、最終金)←見積書に載っていることが多い。
・預金担保がとれるか。
<取得物件>
・謄本を利用して記入。(ネット謄本利用)
・ゼンリン地図を利用して取得予定の宅地を教えてもらう。
・幅員・間口はどのくらいか(公図はA3で1/500縮小なので概算で出すことも可)
<他行の取引>
他行の取引を見て無担保ローンの借り換え提案もする。
<取入書類>
・仮申込書
・個人情報の取扱に関する同意書
・本人確認書類
・見積書
・源泉徴収票

住宅ロ-ン正式申込
〈確認事項〉
・借替の場合基本的には正式申込書からかいてもらう。
・業者が提携先の場合、提携ロ-ン用の正式申込書に記入してもらう必要があったり、抵当権設定手続きや保証料徴収先が提携先となったりするので「提携住宅 商品コードおよび提携先一覧」を利用して確認する。
<ヒアリング事項>
・仮申し込みの時点と変わったことを聞きこむ。
(建築費用、諸費用、返済期間、融資金額等)
→※増額・期間延長・物件変更の場合再申込の必要あり
・建築業者との最終見積・工程表などを見せてもらい実行日をいつにするか、抵当権の設定(持ち分の割合)などについても聞きこむ。
<申込>
・仮申込書の記入方法と同じ。(※訂正印をいただく必要あり。)
・拒絶対象先チェックの実施(仮申込でしていなければ)
・団信加入確認
・住宅ローン申込書チェック表を使用し、申込書の記入内容と勤務実態を確認する。
・「住宅ローン申込書類送付書」と「担保物件評価必要書類確認表」を使用し申込書類を審査部に送付。
・送付書類はすべてコピーし自店保管する。
取入書類は正式申込必要書類に記載
保証会社が担保調査のため写真を撮ることを了承していただく。
担保
公図やゼンリン地図をみて担保物件の取り漏れがないか、前面道路はどうなっているかを確認する必要がある。
公図がわかりにくい場合地番図を取る必要あり。
リフォームの場合はリフォーム前後の写真を撮る必要あり。着工前に写真を撮らせていただくよう依頼。
<条件変更>
・正式審査の案件承認後から実行予定日までに申込人から承認条件変更の申し出を受けた場合、承認条件変更依頼を行う。※実行予定日の1週間前まで(添付参照)
・金額の増額・期間延長・物件変更は不可
<金利協議について>
借入申込書のコピー
団信申込書のコピー
推進カード(公共料金、給振がセットされてるかどうか確認する)
住民票(高齢者または子供のやつが付帯できるか確認するため)
審査決済通知書
審査結果のお知らせ
以上を添付して、住宅ローン回覧簿と一緒にまわす。
該当箇所にマーカーで線を引く。

住宅ローンの金消契約
<必要書類>
・ローン契約書
・金利変更等に関する特約書
・住宅ローン基準金利に関する説明確認書
・保証委託契約書
・抵当権設定契約書
・個人情報の取り扱いに関する同意書(担保提供者分)
・委任状
・借入意思確認記録表
・担保提供者借入意思確認記録表
・振込依頼伝票
・保証会社振込伝票
書類への誤記入を防ぐため鉛筆で下書きする。(特に日付は実行日となるため注意!!!ただし住宅ローン基準金利に関する説明確認書、個人情報の取り扱いに関する同意書は受付日)
<ローン契約書の説明等>
借入要項を順に説明し、お客様に確認してもらいながらみてもらう。
ボーナス増額返済がある場合、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済することを伝える。
・振替口座の確認
・損害金
…繰り上げ手数料(クレジットに加入いただいてる場合100万以上の繰り上げ返済であれば無料と伝える)
繰り上げ返済出来る日は返済日のみであることを伝える。
諸費用は自動で引き落としであることを伝える。
ご理解いただけたら日付、住所、名前記入
金利変更等に関する特約書
順に説明する。
第2条の特約の適用金利、特約期間終了後の適用金利については特に慎重に説明。
特約終了後、再特の必要があり、電話でも受付可能。
返済が遅延していると再特できないこと。
選択しなければ自動的に変動になることを伝える。
<不動産取引>
当日の流れ
物件内容について買主、売主が話す。
所有権移転登記に必要な書類を準備
司法書士がオッケーをだす
<融資実行>
買主側の口座に残余金が振り込まれる。
このとき手付金、仲介手数料、固定資産税等差し引く
売主
仲介手数料、固定資産税支払い
<注意事項>
(担保関係)
登記の内容が現状と違う場合は、滅失されていたら滅失登記をしてもらう必要があると同時に事前の内容で設定し、事後に表題表記変更の差入れ書をもらう必要がある。
【担保物件説明書】
担保物件説明書は最終担保に取る登記状態のものを記載する必要がある。
そのため現在の登記のものは参考にしてはいけない。
【抵当権設定契約書】
債務者兼抵当権設定者
に名前を記入するが、抵当権設定者が夫や親の場合
兼抵当権設定者を二条線で消しその横に削七字と書き、債務者と担保提供者の実印をもらう。
担保提供者のところには抵当権設定者の実印もらう。
また担保提供者の同意書をもらう必要あり。また印鑑証明書、保証会社用と設定用
【新築の場合】
担保差し入れに関する念書をもらう
ここに書くのは竣工予定日と
建物は新築予定物件を記入する。
【融資額について】
融資額は全て振込対応する必要はなく、領収書が融資額以上の取り入れが出来れば問題ない。
例えば先に自分の資金で立て替えで支払いされた場合など
【火災保険】
火災保険は建物が完成してからつける(引き渡しまでは業者の責任となるため)
のが基本となっており、完成後入ってもらえるよう手続きを事前に済ませる。
銀行によって取入する書類は変わってくるかもしれませんが、応用できるところもあると思います!
コピペ全然OKなので、自分なりの職務記述書を作成してくださいね!