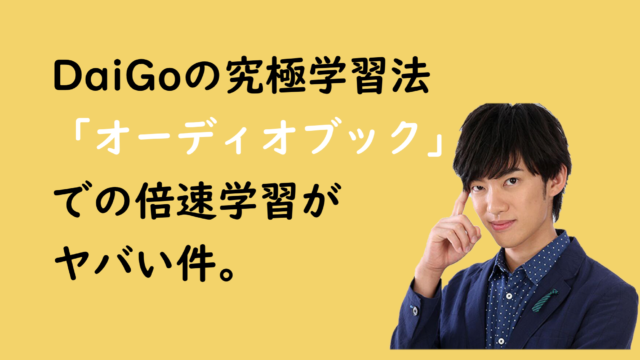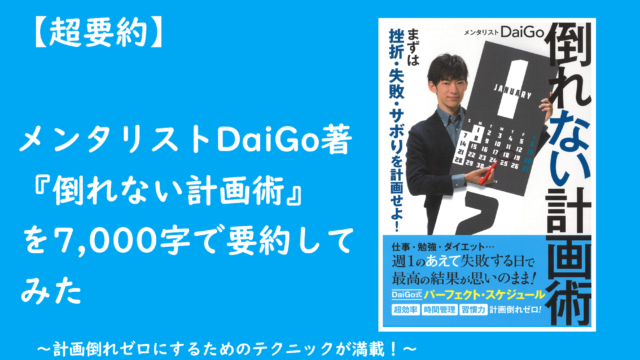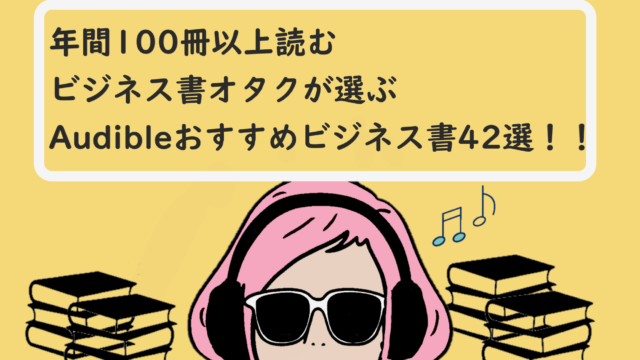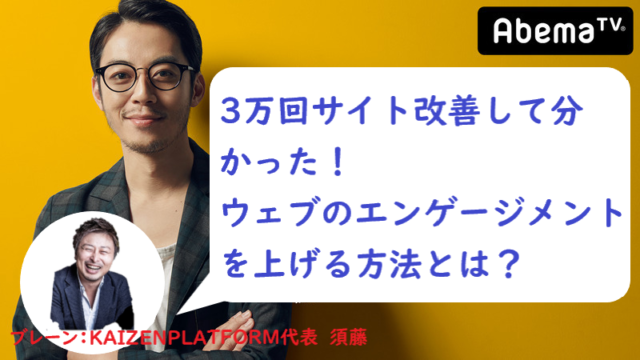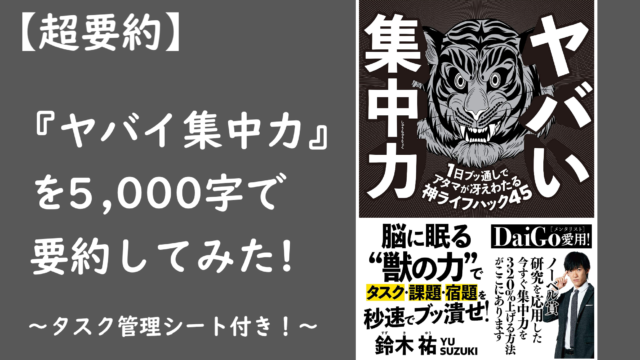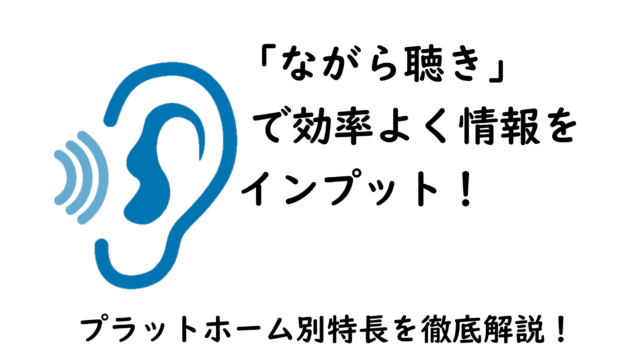どーも半沢くんです。
寒い季節となり、コロナが再度猛威を振るっていることで、業界によってはまだまだ厳しい状況が続いています。
アフター5も控えないといけないため自分と向き合う時間が長くなり、
「このまま今の仕事を続けていてもいいのか?」
とふと考えたりしている人も多いんではないんでしょうか?
今回は、転職を少しでも考えているのであれば是非読んでみてほしい「転職の思考法」を紹介していきたいと思います。
Amazonを覗いてみると、こちらの本は転職に関する書籍の中でもトップクラスの評価を得ており、800件以上レビューがあるにも関わらず、その★は平均4.5と非常に高い評価を得ています。

この著者は北野唯我さんという方で、神戸大学経営学部を卒業後、博報堂に入社。その後、ボストンコンサルティンググループを経て、現在ワンキャリアという就職活動サイトを運営している会社の取締役として活躍されています。

本書では仕事選びにおいてどういう点を重視すべきかどうかを論理的に解説しているのですが、ただ重要な点を挙げているのではなく、ストーリー形式で進んでいくため、非常に分かりやすく「こういう場合は自分はどうすれば良いのか?」ということが非常にイメージしやすくなっています。
転職する上でだれもが悩むであろう、業界・職種選びやエージェントの付き合い方、年代別の転職マーケットで求められることなどに対する答えがこの本には詰まっています。
本書は
- 日本の終身雇用が崩壊していく中で20、30代のキャリアをどうすべきか迷っている
- 失敗しないエージェントの選び方を知りたい
- 良い転職先の会社を選ぶコツを知りたい
という人に最適です。
本書に書かれていることを実践すれば、自分にあった職業を選択することが可能です。
上辺の「転職情報」ではなく情報を見極める「思考の軸」を手に入れることができるので、是非一度読んでほしい一冊です。
(2024/04/25 06:00:26時点 Amazon調べ-詳細)
またこの本は耳で聴くAmazonオーディブルにも提供されており、30日間無料で聞くことができ、無料期間終了後も一冊は無料で聞き続けることが可能です。
本書はストーリー形式のため聞き流しながらでも頭に入ってきやすいのでオーディブルで聴くのがおススメですよ。
転職の思考法の目次は?
はじめに
第1章 仕事の寿命が切れる前に、伸びる市場に身を晒せ
第2章 転職は悪は努力を放棄した者の言い訳にすぎない
第3章 あなたがいなくなっても、確実に会社は回る
第4章 仕事はいつから楽しくないものになっただろうか?
第1章 仕事の寿命が切れる前に、伸びる市場に身を晒せ
本書の中でも一番重要なことが書かれていたのがこの第一章でした。
そのため今回の要約では、第1章を重点的に要約していきたいと思います。
まず、転職を考える上で重要なのは
「自分はその転職市場の中でどのくらいの価値があるか」ということです。
当たり前のことですが、「自分がどれだけ転職したい!」という気持ちがあっても、転職先の会社が自分を求めてくれていないと転職することは不可能です。
そのため、自分の上司(会社)を見るのではなく、マーケット(世の中からみた自分の価値)を見る必要があるのですが、どうやって測るのかというと以下の3つの要素に分けて考えるべきだと著者は言います。

給料の期待値(箱の大きさ)は①技術資産②人的資産③業界の生産性の三つの要素のかけ算で決まります。
3つの要素について一つずつ解説していきますね。
①技術的資産について
技術的資産とは、「価値のある技術をどれくらい持っているか?」ということです。
そして技術資産とは「専門性」と「経験」で成り立っています。
「専門性」とは、法人営業や法人向け新規開拓、会計、税務、プログラミング、デザインなどを指します。
一方で「経験」とは、「職種に紐づかない技術」のことを指し、例えば事業部長の経験や子会社経営、チーフマネージャー、プロジェクトリーダーや業界経験のことを言います。
両方にいえますが、技術的資産と言えるのは、「他の会社でも展開できるかどうか」ということです。ここを押さえておかないとだめです。
そして、マーケットバリューはあくまで相対的に決まるため、市場が求めるスキルでレアなものほど一気に価値が出ます。
また専門性は誰でも学べば獲得可能であるため、年をとればとるほど差別化しにくくなります。そのため20代は「専門性」、30代は「経験」をとるようにすべきです。
そして、普通な人こそ「経験」で勝負すべきだと筆者は言います。
なぜかというと、専門性で他人と差別化するためには圧倒的な努力量だけでなく才能にも深く影響するからです。その反面、経験というのはどこを選ぶかというポジショニングの問題なので考え方と行動の仕方で手に入れることができます。
②人的資産について
次に人的資産についてです。
どの会社でも、そんなに優秀ではないのに上司や先輩だけでなく、取引先の人にも可愛がられ人脈だけで仕事を引っ張れる人がいます。
これこそが「人的資産」です。
転職する市場で考えないといけないのは「自分が転職したとしても変わらず仕事をくれる人はいるか」という点です。
人的資産はどうしても付き合いの長さに比例する側面があるため、年を取るにつれその重要度が増していきます。
優秀な人ほど意外とあの人のためなら人肌脱ごうという「貸し借り」で動いているケースが多いからです。
キャリアは20代は「専門性」、30代は「経験」、40代は「人脈」が重要になっていきます。
③業界の生産性について
3点目は業界の生産性についてです。
実はこの業界の生産性というのがマーケットバリューを測る上で最大の要素となります。
業界の生産性とは言い換えれば「平均一人当たりどれほどの価値を生み出しているか。」ということです。
これを数字で表すのであれば、「一人あたりの粗利」に該当します。
給料というのは会社が生み出した利益から支払われており、この一人あたりの粗利が給料の原資となるため粗利が大きくなればなるほど給料がたくさん貰えるという単純な計算式が成り立ちます。
この一人当たりの粗利というのは会社ごとに違うのは当然ですが、業界によっても大きな差があるんですね。
下は2018年度の業界別利益率トップ10のグラフになりますが、トップ10の業界はどこも給料が高いイメージがあるのは分かりますよね。

産業別のGDPは業界によって最大20倍変わることがあるため、どれだけ技術的資産や人的資産が高くてもそもそもの産業を間違えてしまえばマーケットバリューは高くならないのでこの場所選びが非常に大事になってきます。
この業界の選ぶ際のコツは2つあって、
- 生産性がすでに高い産業
- 伸びている産業
という点。
特に、技術資産も人的資産もない人は上記であげた2つの業界へ転職しないとマーケットバリューは高くならないので注意です。
今自分がしている仕事の「寿命を知る」ための方法

仕事には寿命があり、上記の図の①~④の流れで移り変わっていきます。
①のニッチはまだその仕事が生まれて間もない状態で、「雇用の数が少ないが、替えが効かない仕事」から始まり、順番に②、③に移行して最後は④「雇用の数も少なく、誰でもできる仕事」として消滅していきます。
これが、仕事の「賞味期限」が切れる構造です。
この流れをあらわしたのが下の図です。

この仕事のライフサイクルに沿っていけば、衰退している事業での経験は無効化し、伸びている産業に身を置くことはそれだけで価値がある状態であることが分かると思います。
伸びるマーケットを見つける2つの方法
「伸びる産業に身を置く必要性は分かったけど、どうやって探せばいいの?」
と疑問に思った人も多いと思います。
筆者である北野さんは、その伸びるマーケットを見つける方法についても具体的に述べてくれています。
- 複数のベンチャーが参入し、各社が伸びているサービスに注目する
- 既存業界の非効率を突くロジックに注目する
ベンチャーや投資の動向に着目する方法で、具体的には検索サイトで「××業界 ベンチャー」で検索して調べるというものです。
そして出てきた企業を片っ端から調べていき設立年度が若い会社がたくさんあり、投資もたくさん集まっていれば「伸びているマーケットに人と金が群がっている証拠」であるといえるとのことです。
もう一つは、非効率を突くロジックを持っているかどうか。
伸びるサービスは、業界の非効率を必ず突いてくるので、そのロジックが正しければ遅かれ速かれその企業は成長します。
最近はIT×金融のフィンテック分野やIT×医療などITによって非効率を解決し、規模を拡大させている企業がたくさんあるので、そういった伸びる業界に身を置けばマーケットバリューは間違いなく上がるというわけです。
失敗しない会社選びの3つの基準とは?
業界の選び方が分かれば、次は会社の選び方です。
北野さんは次の3つを会社選びの基準にすべきだといいます。
- マーケットバリュー
- 働きやすさ
- 活躍の可能性
マーケットバリューは先程述べたので、働きやすさと活躍の可能性についてここでは述べていきます。
マーケットバリューが高い会社は多忙なため働きやすさは低くなるのかと思っていましたが、実はそうではなくマーケットバリューが高い会社ほど長期的には働きやすくなります。
なぜなら、会社が順調であれば周囲との人間関係は良い傾向にありますが、業績が悪くなってくるとマーケットバリューがない人間ほど他人の足を引っ張るため働きづらくなる環境ができやすいというわけです。
また、「活躍の可能性」に重点を置くべきなのは特に20代の人で何もまだ強みを持ってない人です。
活躍の可能性を確かめる3つの質問があるので、面接時に聞いてみて確認しましょう!
- どんな人物を求めていて、どんな活躍を期待しているのか?
- 今いちばん社内で活躍し、評価されている人はどんな人物か?なぜか?
- 自分と同じように中途で入った人物で、今活躍されている人はどんな社内パスを経て、どんな業務を担当しているのか?
これらを面接で聞いてみて、的確な回答を得られなかった場合は、その会社に就職するのはもう一度よく考えたほうがいいかもしれませんね。
第2章 「転職は悪」は努力を放棄した者の言い訳にすぎない
第2章に入ると、第1章で押さえた基本的なところから発展してより具体的な転職の仕方について述べられています。
ここでは、書かれていた中でもここは押さえておくべきだという部分をまとめますね!
まずは新卒で入るべき会社と中途で入るべき会社の違いです。
おそらく転職の思考法というタイトルの本であるため、その名の通り就職ではなく転職を考えている人がこの本を手に取ると思いますが、就職と転職の違いをしっかりと意識してから転職に望まないと自分が思うような転職ができないので必ず押さえておきましょう!
新卒で入るべき会社と中途で入るべき会社の違い
◎中途を生かすカルチャーがあるか
→役員が新卒出身者で占められている会社は要注意
◎自分の職種が会社の強み「エンジン」と一致しているか?
→会社の強み以外の職種で入っても裁量権をもちづらい
→自分が行きたい会社の商品やサービスに触れ、どこが好きなのか?をメモする。BtoBの企業は、経営陣や主要メンバーのバックグラウンド(前にいた会社や部署)を確かめれば何を「エンジン」とする会社かが分かる
◎どんな人材でも回るビジネスモデルかどうか
→人材を問わず成長するビジネスモデルは会社としては優れているが、転職する側からみると、マーケットバリューは上がりづらいケースが多い。それでも入社を希望するなら、一通り技術資産と人的資産をつけたうえで、最初から高いポジションで入社すること。
転職エージェントのビジネスモデル
転職サイトや転職エージェントはリクナビやマイナビをはじめとしてたくさんありますが、それらのエージェントがどうやって利益を上げているかを知っておくと、エージェントの言うことを妄信して失敗するような転職にはならないはずです。
たとえば、一人の候補者が、2つの転職エージェントから、A社を紹介された場合、最初に候補者とA社の接点を作ったエージェントが報酬を貰う権利を持ちます。
だから、転職エージェントは他のエージェントと候補者が接触することを嫌い、できるだけ早くたくさん企業を紹介し、受けさせようと急かすわけです。
上記のことを考えると転職エージェントはみんな自己利益のことを考える人、ということになりますが、全員がそういうわけでもありません。
ビジネスではありますが、中にはあなたのことを第一に思って本当に良い転職先を紹介してくれるエージェントももちろんいます。
第2章では良い転職エージェントであるかどうか見分けるための5か条が書かれていたので、是非チェックしてください。
良い転職エージェントの5か条
- どこが良かったか、入社するうえでの懸念点はどこかをフィードバックしてくれる
- 案件ベースでの「いい、悪い」ではなく、自分のキャリアにとってどういう価値があるかという視点でアドバイスをくれる
- 企業に、回答期限の延長や年収の交渉をしてくれる
- 「他にいい求人案件は、ないですか?」という質問に粘り強く付き合ってくれる
- 社長や役員、人事責任者などとの強いパイプがあり、彼らとの面接を自由にセットできる
第3章 あなたがいなくなっても、確実に会社は回る
第2章からの続きで、企業の立場に立ち、企業にはどんな採用方法があってそれぞれどんあ特長があるのかというところをピックアップした章になります。
なぜ、企業は高いフィーを払ってエージェントを使うのか
◎企業にとって、採用方法はエージェントだけではない。チャネルは主に以下の5つがあり、企業から見れば上から順にコストが高いです。
- ヘッドハンティング
- 転職エージェント
- ダイレクトリクルーティング型のサービス
- SNSなどマッチングサービス
- 直接応募、または友人からの紹介(リファラル採用)
企業がエージェントを使うのは、「離婚率が異常に高い」「社員が知人を呼び込む形での採用ができていない」などの理由であることもあります
エージェントが強く勧める会社は、単に採用基準が低い会社(エージェントからすれば、入れやすい会社)にすぎないこともあります
転職エージェントから紹介される案件だけで、転職先を絞ってはいけない。行きたい会社がある程度定まっているなら転職者はすべてのチャネルを自らあたるべきです。
転職後の給料について
すでに給与が高い成熟企業と、今の給与は低いけど今後の自分のマーケットバリューが高まる会社とで悩むことがあれば、迷わず後者をとれ。
マーケットバリューと給与は長期的には必ず一致する(高すぎる給料を貰っている人材はほぼ確実に減給か、肩たたきにあう)。そして、この国はマーケットバリューと給与のギャップを、40代後半になるまで誰も教えてくれない
まとめ
以上が、「転職の思考法」の要約でした。
今回は要点だけまとめていますが、本書はストーリー形式なので普段は本を読まない方でも非常に読みやすい内容となっているので転職を一度でも考えている人は是非読んでみてください。
(2024/04/25 06:00:26時点 Amazon調べ-詳細)
また、科学的な根拠に基づき、「キャリア選択」という正解のない悩みに答えを出す方法を具体的に解説したノウハウ本「科学的な適職」についても要約しています。
本書と併せて読むと、自分に合った仕事は何なのか?どんな転職が自分にとっていいのか?について今までよりも一歩進んだ答えを導きだせるはずです。
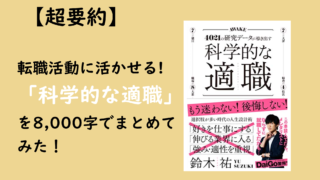
要約だけでもいいので是非一度読んでみてくださいね!
では、また!