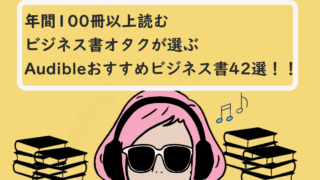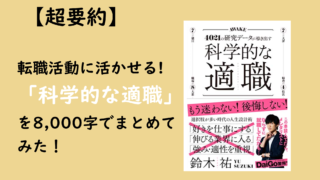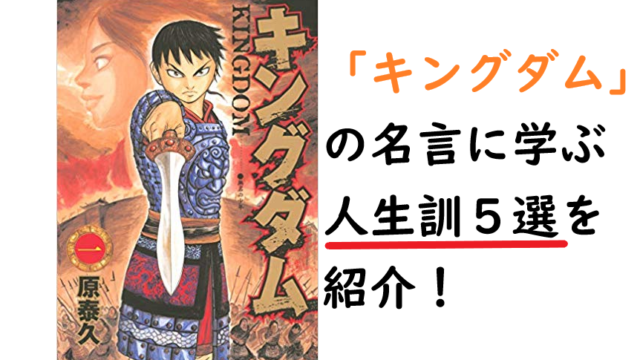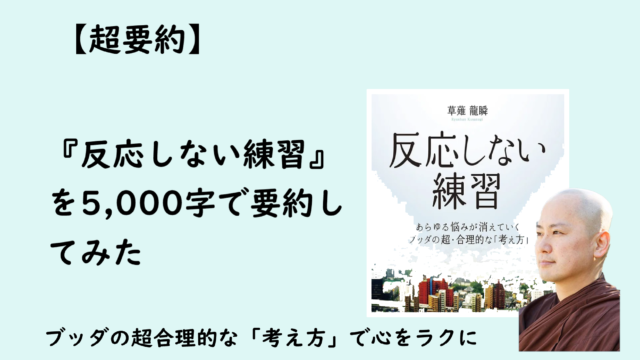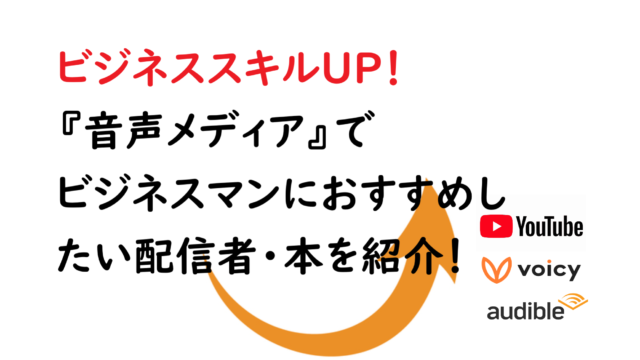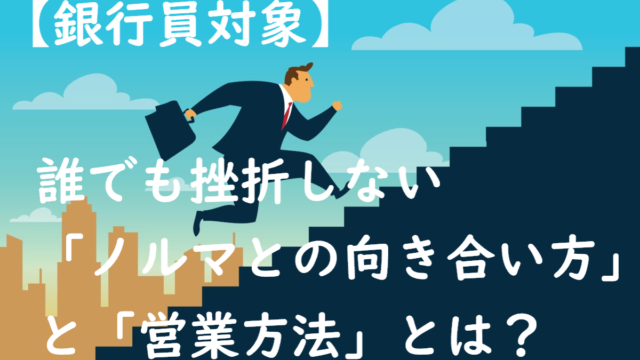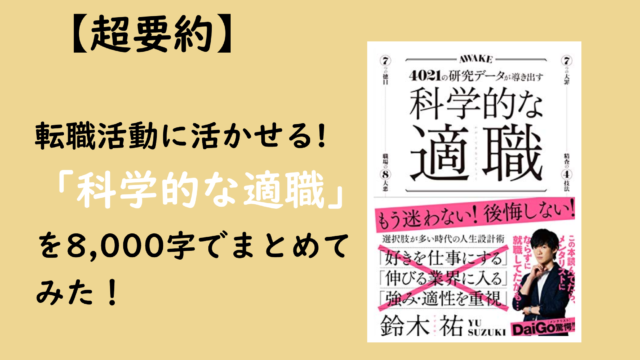どーも半沢くんです。
今回読んだのは、鈴木拓氏著書の「ヤバイ集中力」
これを読んだのは、最近読んだ、メンタリストdaigo著作の「超習慣術」と組み合わせることで高い集中力を保ちながら継続的にブログに取り組めると思ったからです!
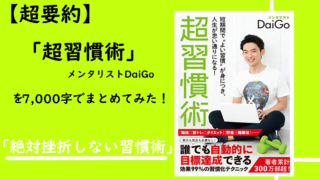
本書はDaioGoさんも愛用している集中力をあげる方法が掲載されており、集中力を上げることについてここまで網羅されている本はなかなかないとのことです。
(2024/04/26 01:20:18時点 Amazon調べ-詳細)
本書で紹介されるメソッドを押さえておけば、集中力を高く維持することが可能となります。
- 仕事に取り組みはじめたのはいいもの、20分くらいしか集中力が続かない
- 副業を始めたけど、始めるまでにスマホをいじってしまい2時間無駄にしてしまう。
- 今回は短期集中でなんとしてもやり遂げたいことがある
という人に最適です。
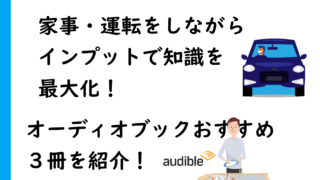
ヤバイ集中力の目次は
序章 獣と調教師…ポテンシャルを400%引き出すフレームワーク
第1章 餌を与える…脳の馬力を高めるサプリと食事法
第2章 報酬の予感…脳内ホルモンを操る目標設定の奥義
第3章 儀式を行う…毎回のルーティンで超集中力モード
第4章 物語を編む…セルフイメージを書き換えて「やる」人間になる
第5章 自己を観る…マインドフルネスで静かな集中を取り戻す
第6章 諦めて、休む…疲労とストレスを癒すリセット法
獣と調教師をどのように操るのかが重要
/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/04/05/000_dv1451981.jpg)
いきなりで残酷な事実ですが、集中力の半分は生まれながら(遺伝)に決まっています。
しかし、残りの半分は訓練して鍛えることが可能となります。
では、どうすれば鍛えられるのか?
「ヤバい集中力」では、「獣と調教師」という比喩を使い、その正体を解明しつつ、方法が語られていきます。
人には獣と調教師という2つの側面があり、その2つの側面の性質を十分に理解するとともに、反対にその性質を上手く利用することで高い集中力を発揮することが可能であると鈴木さんは言っています!

そして、「残念ながら調教師には獣に勝てない」という事実をしっかり理解したほうがいいと著者は述べており3つの教訓が紹介されています。
第1の教訓:調教師は獣に勝てない
第2の教訓:集中が得意な人など存在しない
第3の教訓:獣を導けば莫大なパワーが得られる
問題はそんな獣のパワーが、情報を激増する現代社会で機能不全を起こしているところです。
「情報量が激増する社会では、人間の集中力こそが最も重要な資産になる」にも関わらずです。
そこで、目の前のタスクに気が乗らず、作業のスタートラインにすら立ててない状態のときは、「自己効力感」と「モチベーション管理能力」の2つを持つことが重要です。
自己効力感
「自分は難しいことでもやり遂げれる!」と自然に思える心理状態のこと。この感覚がないと簡単な作業でも難しく感じられてしまい、はじめの一歩をふみ出せなくなる。
モチベーション管理能力
気が乗らないタスクに取り掛かるためには、どうにかしてやる気を引き出して、気持ちを高めていくような環境づくりや管理をすること。
さらに必要なのは注意の持続力を保ち続ける(セルフコントロール)ことです。
成人の限界は平均でたった20分だけで、基本的には脳を効率よく使うスキルを学ぶしかありません。
どのような方法を用いれば獣(本能)を押さえて、調教し(理性)、自分を操る(セルフコントロール)できるかということがこれから紹介する方法を実践すれば可能です!
脳の馬力を高める食事法

第1章では、食事法についてです。
結論からいってしまうと、研究の結果集中力を上げるのに最も効果があるのは、結局「カフェイン」だということが分かったそうです。
そのカフェインの取り方でベストな方法は、以下の通りです。
- 一日缶コーヒー2本分まで
- 起床から90分以内にはコーヒーは飲まない(人間の体は午前6時頃からコルチゾールという覚醒系のホルモンが分泌されるため)
- 緑茶と一緒に飲む
また脳に良い食事をするためのルールとして3つあります。
- 脳に良い食品を増やす
- 脳に悪い食品を減らす
- カロリー制限はしない
【脳に良い食品一覧】
| 【カテゴリー】 | 【一食分の摂取量目安】 |
|---|---|
| 全粒穀物(玄米等) | 握りこぶし1個 |
| ベリー類(イチゴ等) | 握りこぶし1個 |
| 野菜 | 両手の手のひらにのるぐらい |
| 鶏肉、魚介類、豆類 | 片方の手にのるくらい |
| ナッツ類、オリーブオイル | 親指くらい |
【脳に悪い食品一覧】
| 【カテゴリー】 | 【上限摂取量】 |
|---|---|
| バター、マーガリン | 1日小さじ1杯 |
| お菓子 | 週に5食まで(1食ポテチ1袋) |
| 赤肉 | 週に400g |
| チーズ | 週に80g |
| 揚げ物 | 週に1食 |
| ファストフード | 週に1回 |
これらのルールを守れば、おなかいっぱい食べても集中力には問題はなく、脳に良い食品を意識して食べ前と後では、集中力の差が非常に大きなものとなるそうです。
脳内ホルモンを操る目標設定の奥義
![SMARTの法則とは?目標設定法でゴールへの近道を [コンサルタントで働く] All About](https://imgcp.aacdn.jp/img-a/1200/900/aa/gm/article/2/9/5/3/8/3/1539829112/topimg_original.jpeg)
本書で最も重要だといえるのが、この第2章です。
そのため、第2章を重点的にまとめています。
この2章では、「達成感がやみつきになるタスク管理法」として、過去の集中力に関する大量の研究から特に効果が大きいものを激選した「報酬感覚プランニング」というワークシートが紹介されています。
このワークシートが本当に秀逸でこのシートに沿ってプランニングしていけば自然と、自分が成し遂げたいことに集中することができます!
後ほど、図を載せますので保存して是非活用してみてください。
第2章目玉のワークシートを紹介する前に、まず集中力をキープできない人にありがちな2大要素として次の2つが存在しています。
それは
- 不毛タスク
- 難易度エラー
です。
「不毛なタスク」とは?
「この作業は何のためにやっているんだろう・・・」や「この仕事で何が得られるのだろう・・・」などと、思わず疑問を持ってしまうようなタスクのこと。
報酬そのものに意味が感じられなければ、エネルギーが湧かない。
「難易度エラー」とは?
タスクの難しさが自分の能力に適しているかどうかを問題にしています。ベストな集中力を保つには、 難易度をなんとか解けそうなレベルにすることが重要
これら上記の2大要素を排除し、現時点で効果が明らかな対策をひとつの流れにまとめたワークシートが「報酬感覚プランニング」です。
このワークシートに沿って設定すること高い集中力を保持できます。

順に説明していきます。
①「ターゲット」…集中力が続かないものから最も重要なものをひとつ選んで書き込む
②「重要度チェック」…目標を達成しなければならない理由を考えて、大事なものひとつ書き込む
③「具象イメージング」…できるだけ頭のなかで映像をうかべやすい内容に変える
具体例)
目標「企画を作成」→具体に変換「企画書を上司に提出して一息ついたところで映画を見に行く」
④「リバースプランニング」
目標達成までのサブゴールド期日を設定します。しかし、普通に現在から未来に向かって計画を立てるのではなく、最終の目標イメージから現在にさかのぼる形で短期目標を決める。
⑤「デイリータスク設定」…一つのタスクを2~3に分解
具体例)
「企画の概要を箇条書きで書く」という作業に集中できなかった場合、「資料から使えそうな情報を抜き出す」→「抜き出した情報を箇条書きにまとめる」
この5つのステップに沿ってタスク管理をするのがまずは基本となります。
タスクを小分けにするほど作業の難易度が下がり、その分だけ獣も「報酬の予感」を維持しやすくなります。何度か調整を行い、最適な難易度を探してみてください。
報酬プランニング②「実践編」
第1段階で基本設定ができたら、次は第2段階です。
第2段階では、基本設定でリストアップした「デイリータスク」を実際にこなすための作業を行います。

①「デイリータスク選択」
調教師は3つ以上の情報を一気に処理できないので、基本設定で考えたデイリータスクの中からその日のうちに手をつけねばならないものを3~5つピックアップしてください。
②「障害コントラスト」
選んだデイリータスクを達成する際に、発生しそうなトラブルを書き出します。
例えば)
・どんな考え方が目標の達成を妨げているのか?
・どんな行動が目標の達成を妨げているか?
・どんな癖や習慣が目標の達成を妨げているのか?
・どんな思い込みの目標の達成を妨げているのか?
・どんな感情が目標の達成を妨げているのか?
この障害コントラストで使ったのは「心理対比」と呼ばれるテクニックです。
20年に及ぶデータの蓄積を持つ技法で、目標に取り組むモチベーションを高め、 作業の集中力を上げる働きを持ちます。
「もう目標を達成したから何もしなくていいだろう」
ゴールまでの道のりを詳しく想像したせいで、獣が既に目標を達成してしまったかのように勘違いしたわけです。心理学的には「ポジティブ思考の罠」と言われる状態です。
「理想の未来を思い描こう!」や「根拠のない自信を持とう!」といった自己啓発系のアドバイスが失敗に終わりやすいのも、同じようなメカニズムが働くのが原因です。
「心理対比」は、この問題を解決してくれます。意図的にトラブルの発生をイメージしたおかげで、獣は「まだゴールについていないのだな」と認識し、そのおかげで前に向かうモチベーションを取り戻してくれるからです。
ポジティブ思考を使う時は、必ずネガティブ思考をセットにしてください。
③「障害フィックス」
前のステップで想定した障害に対して、あなたが取れそうな対策を考えて書き込みましょう!
例えば、
障害:「スマホの通知で気がそれる」→対策「スマホの通知を全て切る」
障害:「とにかくやる気がわかない」→対策「とりあえず5分だけ作業に手をつけてみる」
障害:「エクササイズをサボってしまう」→対策「サボったら友人に罰金を払うと事前に決めておく」
このステップは「心理対比」を補強するために行います。
④「質問型アクション」
「デイリータスク」について、それぞれ「 質問型アクション」を設定します。デイリータスクの内容を、次のフォーマットに変換してください。
・「自分の名前」は、「時間」に「場所」で「デイリータスク」をするか?
具体的な例)
デイリータスク:企画書の文章の見直しする
質問型アクション:山田太郎は、午前9時に会社の自分の席で企画書の見直しをするか?
わざわざタスクを質問形式に変えるのは、「問いかけ行動効果」と呼ばれる心理現象に基づいています。
「宣言文よりも質問文の方が行動を変える力を持ち、その作用は6ヶ月が過ぎても続く」
との報告が得られています。
「質問型アクション」で集中力が上がるのは、質問文の方が、 獣へ訴えかける力が強いからです。
⑤「現実イメージング」
質問型アクションを達成するまでのプロセスを、できるだけリアルに頭の中に思い描くこと。イメージのディティールが細くなるほど集中力は上がります。
「トレッドミルで走る時の足の裏の感覚」「企画書を作る最中に聞こえる周囲のノイズ」など、五感に訴えるような情景を細かく頭に浮かべることがポイントです。
⑥「固定式ビジュアルリマインダー」
獣は目の前のものにしか反応しないため、定期的に「質問型アクション」のことを思い出させてやらないと、すぐに忘れてしまいます。
リマインダーの手法は何でもよく、スマホのアプリを使ってもいいですし、手帳に書き込んでも構いません。それよりも大事なのは、リマインダーを常に目に入る場所に置いておくことです。
リマインダーとは、作業のスタートを思いださせる機能よりも、一旦気がそれた獣の注意を引き戻す働きのほうが重要です。もし作業中に気がそれても、質問型アクションの文章が目に入れば、獣は本来の作業に戻りやすくなります。
ゲームやネットにふけってばかりの人生とは他人から獣を操られ続けることに他ならず、そこにあなたの本当の自由は存在しません。
それが嫌なら、すべてを自分でコントロールする以外に道はないのです。
第3章では、毎回行うルーティンが集中力に大きく関わっているという点について記載されており、ここまでが獣を動かすことを目的に書かれた章になります。
第4章以降では調教師を鍛える上で必要なテクニックが記載されていたので、詳しくは本書を読んでみてください!
神ライフハック45をすべてマスターすれば、確実に集中力が身につきなりたい自分になれるはずです!
また本書以外にも、メンタリストDaiGoさんの「超集中力」も集中力を高める方法を、研究データに基づき網羅的に記載されているのでおすすめです。
是非参考にしてみてください!
ではまた!