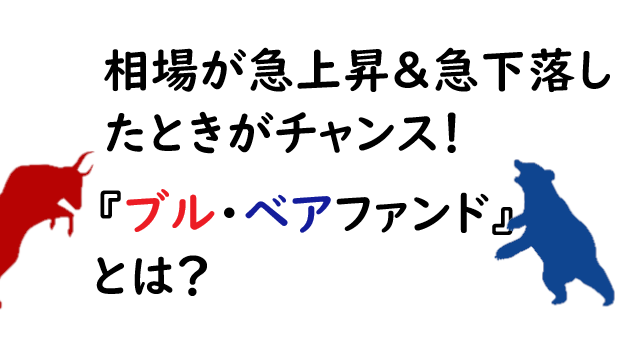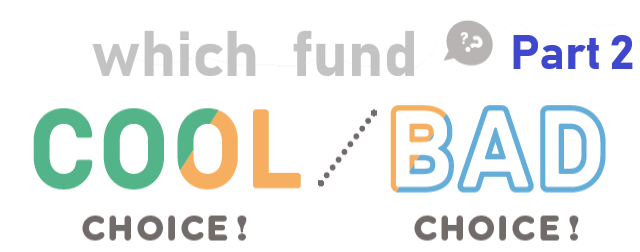過去3回に渡って投信購入のポイントを説明してきました。
この記事では実際の目論見書を用いて一つづつ説明していきますのでゆっくり見ていきましょう!!
もっともポピュラーであるインデックス225を参照に解説していきたいと思います。
こちらが目論見書の表紙です。

投資信託を販売する場合には必ずこの目論見書をお渡しする必要があるのですが、まず表紙を見ていただけたらこの投信は
追加型・国内・株式・インデックス型と書かれています。
ということはこれらはいつでも購入ができるタイプの投資信託で国内の株式でありかつなにかしらのベンチマークに連動するタイプの投資信託ということが分かります。
こちらは目論見書2ページ目です。

ここでは商品分類と属性区分が記載されています。
対象インデックスには日経225と記載されていますので日経平均225をベンチマークと連動を目標としたファンドとなります。また決算頻度が年1回と記載されていますがここも重要な点となります。
決算についてはまた別の記事で説明したいと思います。
下の赤丸には委託会社が掲載されています。
委託会社とは投資信託を設定し、運用する会社のことをいいます。 投資信託委託会社の主な業務には、投資信託約款の作成、目論見書の作成、受益証券の発行、信託財産の運用指図、運用報告書の作成などがあります。

投資信託の場合、上記のように実際投資信託を販売する「販売会社」と設定・運用を行う「委託者」とその信託金を管理する「受託者」の3つに分けることができます。
とりわけ委託者は重要で、実際に数多ある株から選定しファンドを作っているのでファンドマネージャー次第で同じようなジャンルのファンドでも投資比率や選定会社の違いで運用成績が大きく異なることもあります。
続いて目論見書3ページ目です。

こちらには投資家が確認すべきファンドの特色について列挙されています。
投資信託を選ぶ上で一番最初に確認しましょう。
つづいて4ページ目です。

上記のようにこちらには投資家が確認すべきリスクについて列挙されています。
価格変動リスク、流動性リスク、信用リスクと3つありますが、海外へ投資する投資信託の場合為替リスクやカントリーリスクなどもあります。細かいリスクの意味は理解しなくても大丈夫ですが概要だけでも確認はするようにしましょう!
続いて5ページ目です。

この5ページ目は非常に重要な購入判断基準の一つになる平均騰落率が記載されています。
騰落率というのは株式などで暴騰や暴落というのがありますが、購入したときの基準価額を基準にして、投資信託の価値がどれだけ変化したかというものになります。
式で表すと
【騰落率(%)】=【購入時との基準価額の差(円)】÷【購入したときの基準価額(円)】×100
です。
「騰落」とは上がり下がりを意味します。株価や為替で使われる「急騰」や「急落」のほうが一般的かもしれません。
ここの騰落率で注意すべき点は
年平均の値ではなく、全期間の数値であるという点です。
数字で例を挙げてみます。3年間で基準価額が1万円から2万円になった場合。分配金はゼロとします。騰落率はさて、何パーセントになるでしょうか?
騰落率は
(2万円-1万円)/1万円=1
100を掛けて%に直して、騰落率100%となります(もし分配金が2000円あったとすると、騰落率は120%となります)。
1年あたり平均すると33.3%ですが、「3年間騰落率100%」と言った表現が一般的なようです。
騰落率は、どれくらい上昇したか下落したかを示す指標ではあるのですが、その期間がいろいろあるので、預金などの利率や利回りと同じ感覚でいると混乱する可能性があります。
利率も利回りも1年を基準にしているので、騰落率も1年あたりの数値に直せばもっとわかりやすくなると思うのですが、ホームページでも1年あたりの数字に直しているところがあります。
それが価格.comです。
騰落率を1年あたりの数字・年率に換算したものが併記されているのでここを確認し運用成績を確認していきましょう。
次に6ページ目です。

ここでまず確認しておきたいのは右上に書いてある2017年12月29日現在というところです。目論見書はファンドにもよりますが半年や一年に一回更新されるものもざらにあるためここを確認しておかないと
「他のファンドと同時期のものを比較する」という視点が抜けてしまうため正確な比較ができなくなってしまいますので要注意です。
あと基準価格は株でいう株価のようなものですが、ここで重要なのは純資産価格です。
純資産価格の重要性を問う人はあまりいないのですが実は非常に重要な投信購入ポイントとなるのを読者の方は理解したほうがいいと思います。
何故なら純資産額の推移からこのファンドは買い基調にあるのかそれとも売り基調にあるのかが一目でわかるからです。
下の水色の部分が純資産額の推移なのですが、基準価格が上昇しているにもかかわらず純資産総額が減少傾向にあることが分かります。このことから今この投信は今後基準価格が上昇するためそのまま保有しておこうとしている人より、割高になってきたし一旦利益確定のために売却した人のほうが多いためであるということが分かります。
また純資産総額についても注意してみる必要があります。
日経225は初期に作られた投資信託のため純資産総額は2,000億と資金が潤沢にありますが、最近できたばかりの投資信託であると純資産が5億以下の投資信託もあります。
あまりにも純資産額が少ないファンドの場合、急にファンドが売られだすと運用できない水準までに下がることがあります。その場合は信託期間を無視して繰上償還(強制終了)となってしまいますので注意が必要です。
ファンドの償還には「満期償還」と「繰上償還」があり、その意味は大きく異なります。
ファンドには設定日とともに信託期間終了日(満期日)があらかじめ決められているケースがあります。
この満期日にファンドを償還する場合は、「満期償還」と言われ、償還するために特別な手続きは必要ありません。
一方で、信託期間を「無期限」としているファンドを償還する場合や、あらかじめ決められた満期日より前にファンドを償還するためには、「繰上償還」という手続きが必要となります。
ファンドの目論見書などを見ると、残高減少で運用が困難になった場合などに備えて、「受益権口数が○○億口を下回った場合等は、償還となる場合があります」といった繰上償還の条件が記載されていますので、残高の推移などを見ながら繰上償還の可能性を判断することができるのです。
元銀行員直伝!!絶対にわかる!【目論見書見方編②】に続く・・・